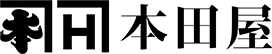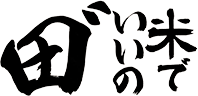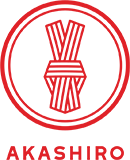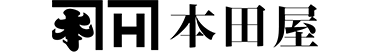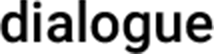理の調和と軸立て
重なり合う理から地域振興の軸を立てる。人に限らず万物は互いの関係性から我の存在を認識する。その関係性はいくつかの理に従い、持続可能な理の調和の中で存在している。人の暮らし、つまり地域社会においても同じであり、地域振興を考えるにあたり“理の調和と軸建て”の思想があるか否かで、共感性や持続可能性は変わる。
私たちは、地域振興においてさまざまな理の文脈を洗い出し、強みや弱みを整理し、調和する色味を見つけ出す。その調和する理に、住民の意思ある熱量を掛け合わせることで、地域振興の軸建てをする。私たちの役割は、地域に存在するさまざまな理を紐解き、取捨選択し、紡ぎ調和し、共感をつくること。その専門性を活かし、持続可能な地域振興のコンセプトをご提案いたします。